シェブロンB19

本国仕様のChevron B19。 納屋のような小さなファクトリーで作られていたという。出典:http://www.conceptcarz.com/
世界選手権でも活躍したイギリスのバックヤード・ビルダー「シェブロン」のプロトタイプマシン。
田中弘により初めて日本に持ち込まれたB19は、コンパクトなエンジンと車体に関わらず速さと信頼性を兼ね備えていました。
兼ねてから将来的には2リッタープロトタイプカーによる選手権を目指していた富士GCにあって、ローラT212と並び多くのプライベーターの参戦を促したパイオニア的存在のマシンです。
ローラT212

写真は本国仕様のLOLA T212。後継であるT280、T290が輸入された後にも3年以上に渡り活躍。日本に輸入されたのは1台のみだった。 出典:http://www.motorstown.com/
高原敬武が日本に持ち込んだのは、シェブロンと同じく英国生まれのローラ・T212。
「高原レーシング」はその後様々なマシンを導入し、77年にはあの「紫電」を走らせたことでも知られていますが、当時の高原はまだ20歳、無名の新人でした。
2リッター超のエンジンが許された最後の年である72年にはローラT280を投入、更に翌年73年には2.0LのT292で高原は初のチャンピオンに輝くことになります。
このT212とシェブロンは共通して比較的全幅が狭いナロー・トレッドで、長い直線の富士では空気抵抗が少なく、これが有利に作用したといわれます。
その後しばらくこのパッケージングは”GCで勝つためのセオリー”として定着していきました。
2リッタープロトタイプの可能性
富士グランチャンがはじまった1971年、それは各クラス混走という何ともカオスなレースでした。
国際規則のグループ4から7までが混走し、優勝を狙う強豪チームはポルシェやマクラーレンを投入。
モア・パワーで争われた日本グランプリの残響をまだ残していた時期といえます。
そんな中行われた富士GC初年度の最終戦「富士マスターズ250キロレース」では、生沢徹のポルシェ917と、22歳の若さで独力Can-Amに出場していた大型新人・風戸裕の一騎打ちとなります。

生沢の持ち込んだ917はレンタルとはいえ、大会ポスターになるほどの注目株だった(Gulfカラーでは無かったが)。出典:http://www.ne.jp/asahi/60srace/models/
ポルシェ初のルマン優勝マシン、917Kは美しいグリーンのボディを纏い、生沢は正に必勝体制。
対する風戸は、ポルシェから直接買い付けた908Ⅱスパイダー(917の前モデル)で参戦。

生沢徹の917K。4.5L水平対向12気筒エンジンは520馬力を発生したが、富士用のセッティングがマッチしなかった様でドライビングには苦戦を強いられたという。出典:http://s90.photobucket.com/
加えて2台のマクラーレンM12を走らせる酒井レーシングは、Can-Am仕込みの7.0LシボレーV8で700馬力という圧倒的パワーでぶっちぎりのポールポジションを獲得します。
しかし本戦でマクラーレン勢は、マシントラブルにより後退。結果はルーキー・風戸が生沢を下し、250キロの長丁場で見事勝利を飾ります。
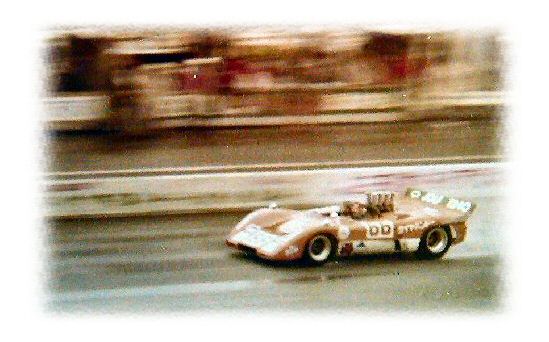
雨の富士を疾走する酒井正のM12。69年日本グランプリで日産R382が記録したファステストラップを更新する程の速さを見せた。出典:http://www.mmjp.or.jp/
しかしより注目すべきは生沢に次ぐ3番手、シェブロンB19を持ち込んだ田中弘でした。
2リッターで240馬力ほどのパワーながら驚異的な速さと安定性を見せた上、ポルシェに比べれば圧倒的に安価だったこのマシンが見せた速さはまさに鮮烈。
この走りが多くのプライベーターに新たな可能性を示し、のちに2リッタープロトタイプで争われることになるGCの原点を築いたのです。
「グランチャン」独自の魅力
73年からは2リッター以下のエンジンのみで争われることになった富士GC。
若きアマチュア達の熱い走りと見慣れぬ海外製レーシングカーが人気の核となり、やがてメーカーのワークス・ドライバーも盛り上がりを見せるGCに注目、続々と参戦を開始します。

高橋国光選手のMARCH 73S 出典:http://muku2.dip.jp/ayashi/
参戦車種はまさに百花繚乱となり、ローラ、マーチ、シェブロン、アルピーヌを始め、国内からもいすゞや風戸裕が旗揚げしたNOVAエンジニアリングなどが参戦。
さらにそれらのマシンは輸入したままの姿ではなく、超高速コース・富士スピードウェイに特化したオリジナリティ溢れるカウルをまとっていたのです。

衝撃のフォルム。出典:http://www.geocities.jp/nakadacara/
この時代の各車は、未だ謎多き「空力」との戦いの果てに、実に多様なデザインを持っていました。
あるものは垂直フィンを立て、またあるものはロングテールに巨大なリアウイングを装着したり…
風洞実験など持ち込まれていなかったこの時代は、プライベーターたちがクラフトマンシップをありのままぶつける野生的なステージでした。
というより、正解が分からず「やってみるしかなかった時代」とも言えるかもしれません。

衝撃のフォルム2。http://www.geocities.jp/nakadacara/
そして多くのエンジニアが、「それこそがGCの魅力だった」と振り返ります。
たとえば1976年のGRD S74を例にとれば、本国仕様との違いにもはや衝撃を覚えます。

本国のGRD-S74。出典:http://www.preloved.co.uk/

生沢選手のGRD S74。このカウルは由良拓也氏が手がけた改良・後期型。出典:http://www.geocities.jp/nakadacara/
まさにまったくの別物…同じマシンとは思えませんね。
ちなみにこのGRD S74は、生沢徹のドライブで1977年のチャンピオンを獲得。
「スター健在」を世に知らしめたマシンでもあります。
洒落者として知られていた生沢の「見た目へのこだわり」は相当に造詣が深く、カラーリング、ステッカーのバランスまで完璧なスタイリング。その速さも相まって注目の的でした。

色褪せないセンスを感じる生沢選手のマシン。出典:http://www.geocities.jp/nakadacara/
対して「無冠の帝王」と言われた高橋国光、GCの舞台で「日本一速い男」に登り詰めたともいえる星野一義。
そして圧倒的強さを誇り3度のGC制覇を果たした高原敬武…などなど、玄人揃いの一流ドライバーによる戦いは毎戦白熱し、当初日本グランプリの”代わり”だったはずの富士GCは、全く新しいレース文化を作り上げていったのです。
更なる発展への模索
2Lプロトタイプの規定はそのままに1シーター化が許された79年以降、F2のシャシーを用いることが常識となり、カウルも「GCマシンの完成系」といえるムーン・クラフト・スペシャル(MCS)のほぼほぼワンメイク状態となっていきました。
F1で可能性が示されたウイングカー構造を持つマシンが台頭し、コーナリングスピードが飛躍的に向上。
富士スピードウェイ1周のラップタイプも1分15秒台という脅威的な速さに到達します。

星野一義選手のMCS4。中嶋悟選手との因縁の対決が熱かった。出典:https://www.mooncraft.jp/
ウイングカー構造については、若き高橋徹が最終コーナーで事故死したことをきっかけに83年いっぱいで禁止され、翌年からはフラットボトム規定を導入。
より安全面への対策が強化されていきました。また、旧富士スピードウェイのBコーナー(ダンロップコーナー)も低速化を目的にこの時追加されています。
この頃には風洞を用いるコンストラクターも現れ始め、「クラフトマンシップ」よりも「風洞の数値」が絶対的な意味を持ち始めました。
しかし実に皮肉なことですが、GCはテクノロジーの進化の果てにウリだったそれぞれのマシンが持っていた個性が失われはじめ、徐々に人気が低迷していくこととなるのです。
”グラチャン”が生んだもうひとつのビッグ・イベント
70年代中盤ほどの魅力を失ったとはいえ、当時富士GCというイベントはまさに日本のモータースポーツの最高峰。
そして、そのウィークエンドで本戦以上の人気を博すイベントが誕生することになります。
BMW M1、TOM’Sのセリカターボ、トミカスカイライン、ニチラシルビア…巨大なチンスポイラーとリアウイング、地面すれすれの車高、そしてビッグタービンを積むが故のド派手なアフターファイア…
そのスタイリングを若者たちが真似して「グラチャン族」という人種をも生み出してしまったセンセーショナルなそのレースが「前座」だったという事実に驚きます。
1979年にはじまった「富士スーパーシルエットシリーズ」は、東名高速に大渋滞を引き起こすほどの”社会現象”となり、スーパーカーブームに沸く日本の若者たちにとてつもない刺激を与えました。

出典:http://japanesenostalgiccar.com/
そして、日産が日本グランプリ以来モータースポーツにおけるワークス活動を再開し「NISMO」を立ち上げたのはこのレースが大きなきっかけであり、また「ハコの星野一義」を復活させたのもこのレースでした。
ちなみに、このスーパーシルエットに続き1984年に始まったJSS(ジャパン・スーパースポーツ・セダン・レース)は、グループA規則を発展させたフルチューン・GTマシンで争われ、1994年に全日本GT選手権に編入されるまで続きます。
裏を返せば、スーパーGTの直接の祖先とも見れるイベントだったのです。
まとめ
富士GCはその後、89年シーズンで幕を閉じます。
最終年は「グランチャンピオン・シリーズ」として国内のサーキットを転戦するシリーズに発展。
エンジンも3.0Lに拡大され、いわば「カウル付きF3000」というレギュレーションで争われました。
一方で、トップフォーミュラであるF3000や、グループAなどのツーリングカーレースがシリーズ戦として成長し、既にGC人気は下火という状況。
このような中、GCは終わるべくして終わったと言えるかもしれません。

出典:http://gazoo.com/
日本のプロフェッショナル・モータースポーツの礎となり、数々の名勝負・そしてスターを生んだ富士グランチャンピオン・レース、いかがでしたでしょうか。
時代の移り変わりとともに「トップカテゴリー」は常に変化し、ファンの関心もまた変化していくのは当然のこと。
しかし、レーサーがいて、サーキットがあって、レーシングチームがある限り、決してレースの興奮が失われることはありません。
あれほど熱狂を呼んだ富士グランチャンでさえも終焉を迎え、それでも尚、日本のレースシーンが発展を続けていることがその証拠といえるのではないでしょうか。
※参考文献
Racing on No.411 富士グランチャン──2座こそGC
日本の名レース100選 Vol.014 ’71 富士マスターズ250キロ
[amazonjs asin=”B0017TAHP6″ locale=”JP” title=”青島文化教材社 1/24 グラチャン No.07 ケンメリ 4Dr”]
Motorzではメールマガジンを配信しています。
編集部の裏話が聞けたり、最新の自動車パーツ情報が入手できるかも!?
配信を希望する方は、Motorz記事「メールマガジン「MotorzNews」はじめました。」をお読みください!









